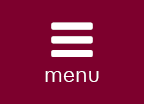英文学・ヨーロッパ思想史(平野ゼミ)※2025年度不開講
| 教員氏名 | 平野 幸治(ひらの こうじ) |
|---|---|
| 職名 | 教授 |
| 専門分野 | 英文学・ヨ-ロッパ思想史 |
ゼミのテーマ
19世紀末から21世紀初頭の英文学において、「拡大する世界と縮小する国家」のあり方の中で個人の内面の変化や個人と社会との関係はどのように形成されてきたか。特にMary ShellyやE. M. Forster やKazuo Ishiguroの作品を中心に「私を作る」という観点と「女性はどのように述べられてきたか」というnarrativeの手法から小説を研究する。
このゼミでは、どのようなことを、どのように学べるか
文学作品を英語で読み、テーマをグループで討議し、プレゼンを行い「協働性」の経験とスキルを獲得する。プレゼミでは、identity, women's liberation, women's empowerment といった用語をキーワードに18世紀末から19世紀初頭の女性の作家たちが新しい世界を先駆的に開拓し、新しいジャンルである「小説」の成熟に寄与した代表的な作品を研究する。シンボルとして『フランケンシュタイン』を討論した。ゼミⅠではKazuo Ishiguroの3作品The Remains of the Day, Never Let Me Go, Kurara and The Sunを扱い、物語の解釈やシンボルの意味を考える。またShakespeareの劇『リア王』等を素材に研究の方法を紹介する。プレゼミやゼミⅠでは、English Literature : A Very Short Introductionを共通テキストに、「物語はどこから始まるのか?」、「物語の終わりは?」、「読者はどこまで作者に近づけるか」等の視点から文学を考察する。ゼミⅡでは、個人と社会との「関係性」にポイントを置き、個人の内面の形成と社会の受容の関わりをForsterの評論を援用しながら考える。互いに討論し、文章化し、成果の発表等の協働性を促す活動で学生は自律的に文献研究ができるようになる。
このゼミで学んだことは将来どのように役立てることができるか
“I-S-E-E”を身につけ、将来自律して考えられるようになる。“I-S-E-E”とは、① Illustrate (立証する能力):自ら、課題を発見したり、仮説を立てたりすること ② State (人に述べる能力): 強制されなくても自ら進んで何かを述べる気構え③ Elaborate (改善する能力): 意見や考えを改善したりさらに洗練したりする思考力 ④ Exemplify (例示する能力): 人に説明するために意見や考えを具体化する力、このような4つの力が身に付き、自律して考えられるようになる。“I-S-E-E”とは汎用性のある能力。さらに、ゼミ活動で得た「読書の習慣化」、「文章を書くことの日常化」、「一所懸命にやることの意義」と「対話の愉しみ」は、今後の人生を豊かにしてくれる。ゼミで身につけた“I-S-E-E”は、近接的な将来には進路に関わる文章作成や面接の際の人対応能力に、中・長期的な「将来」には、自律的に考え、対話を不安がらず、文学を読み続ける喜びに有効と思われる。
学生へのメッセージ
昨今の日本の高等教育において「人文学」は冬の時代である。人文学を英語ではhumanitiesと呼び、人文学とは包括的な文言(an umbrella word)である。人文学という「傘」の中に哲学、文学、宗教、芸術、歴史や言語等の大学ではお馴染みの学問分野が肩寄せ合っている。言わば、人類の所産であり記録である。このゼミでは文学研究を中心に行う。「文学研究はどのようにあるべきか」という問いは、19世紀末から20世紀初頭の英国の大学の問いでもあった。ゼミでは、「文学とは?」と大きな問いから「この文章の意味は?」という問いまで、「問いを持つ」ことの意義や「問いを生きる」ことの意味を考える。観劇・ゼミ合宿の授業以外の活動はコロナ禍では難しいが、記憶を育む思い出は日常に存在する。興味を持った学生は、DVD『めぐりあう時間たち』と『アマデウス』を見てもらいたい。教員の研究室の扉に掲示する文書にも注意して頂きたい。研究室の扉は、比喩的に言えば、「文学の扉」であり「未来への扉」でもある。